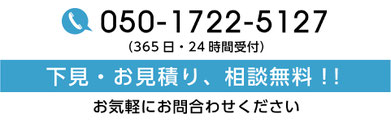総務省では、社会問題になりつつの空き家数などの住宅に関する事項について調査を実施しています。
空き家率は13.5%と過去最高
住宅のうち空き家についてみると、空き家数は820万戸となり5年前に比べて63万戸(8.3%)増加しました。
空き家率(総住宅数に占める割合)は、平成10年に初めて1割を超えて11.5%となり平成25年には13.5%と20年に比べ0.4ポイント上昇し空き家数、空き家率共に過去最高となりました。
別荘等の二次的住宅数は41万戸で二次的住宅を除く空き家率は12.8%となりました。(総務省調べ)

空き家率が最も高いのは、山梨県の17.2%
平成25年のデータですが、別荘等の二次的住宅を除いた空き家率は山梨県の17.2%が最も高く次いで四国4県が続いておりいずれも16%台後半です。
空き家率が最も低いのは宮城県の9.1%、次いで沖縄県が9.8%、山形県、埼玉県、神奈川県及び東京都がいずれも10%台となっています。(総務省調べ)

増加した空き家63万戸のうち一戸建が8割を占める
5年前と比較して空き家は62.8万戸増加しましたが、建て方別にその内訳をみると一戸建の空き家が49.6万戸で79.0%を占めており長屋建が3.9万戸(6.2%)、共同住宅が8.9万戸(14.2%)、その他が0.4万戸(0.6%)と一戸建の空き家の増加が著しいことが分かります。
また、建て方別の空き家の種類別に増減数の内訳をみると一戸建の空き家は、増加した49.6万戸のうち49.4万戸(99.6%)が「その他の住宅」となっています。(総務省調べ)
平成25年の古いデータですが、日本全国の各市町村で増加傾向にあり社会問題でることがわかりました。空き家片付けセンターでは、この社会問題解決に向けて取り組んでいきます。なぜなら様々な問題が予想されろからです。

増え続けると予想されている日本の空き家問題には2つの大きな原因があります。
1つ目は、高齢化社会が進む日本全体の問題で、団塊世代の相続が進み、空き家が急速に増加すること、2つ目は、空き家所有者自身が空き家の管理や活用について問題を抱えていることです。
空き家が地域で問題とされる1つ目の理由は、空き家が増えているということ。
2013年の総務省調査によると全国の空き家数は約820万戸、全住宅の7戸に1戸が空き家という状況です。これが、2033年頃には空き家数2,150万戸、つまり全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうという民間予測となっているのです。
「空き家」は、以下の4種類に分類されます。
- 売却用・・・販売中の空き家。不動産会社が管理
- 賃貸用・・・入居者募集中の空き家。不動産会社が管理
- 二次利用・・・普段使っていない別荘など。所有者が管理
- その他・・・上記の3種類以外。所有者が管理
空き家は4つの種類に分類され、中でも問題になっているのが売りにも、貸しにも出しておらず、定期的な利用がされていない状態の「その他」に分類される空き家(2013年時点で318万戸)です。
「その他」の空き家が問題となってしまうのは、他の空き家に比べて今後急速に増加すると予想されています。
空き家が発生する最も一般的な原因は、自宅を所有する高齢者が老人ホームなどの高齢者住宅や子供宅などに転居することです。今後、団塊の世代を含めた高齢者は急激に増えていきます。それに伴い、空き家もどんどん増える。特に利便性の良くない地域にある住宅街では空き家が一気に増加すると予想されています。
空き家が増えるということは、その地域に住む人が減っているということです。そうすると、その地域の活力が低下するだけでなく、道路や水道、電気といったインフラを維持することが難しくなってしまいます。例えば、道路の利用家族数が半減してしまった場合、1家族あたりの道路維持の負担は倍となってしまう、他にも、スーパーや銀行、クリニックなど、生活に欠かせない施設の撤退も起きてしまう、空き家の増加はその地域の魅力をますます低下させてしまう原因となってしまうのです。
空き家所有者の抱える管理や活用の問題
2015年5月に空家等対策特別措置法が施行され、「空き家問題」という言葉を耳にする機会が多くなっています。空き家問題は所有者側の視点ではなく、近隣住民側の視点で語られることがほとんどです。その結果、「空き家は地域の景観や安全を損なうものである」という負のイメージがついてしまいました。
しかし、空き家を巡る問題のほとんどは、所有者が悪で近隣住民は被害者という単純なものではありません。所有者自身も、空き家の管理や活用について問題を抱えていることが多いのです。そして、所有者が抱える問題の多くは、法律や税制、もしくは物理的な問題であることが多いため、簡単に解決することができないのです。
所有者が抱える空き家問題
空き家の多くは高齢者が住んでいた自宅もしくは親から子供たちが相続した実家です。そのため、空き家には家族との想い出が詰まっており、利活用することに抵抗があるという方が多いそうです。
親が自宅を所有している場合
高齢になる親が老人ホームなどの高齢者住宅や子供宅などに転居して自宅が空き家になった場合、自宅を利活用するにはいくつもの壁があります。片づけを始めても昔のことを思い出してなかなか整理が進まなかったり、最期は家に戻りたいと思っていたり、認知症を患い利活用の判断ができなくなってしまっていたりといったものです。たとえ、子供たちから管理が大変だという理由などから売却を勧めても、同意してくれる親は多くありません。このようなことから高齢者の自宅は長い間、空き家状態になってしまっているのです。
子供が実家を相続している場合
子供たちが相続した後も実家の利活用は簡単ではないのです。子供たちは実家から離れた場所に住んでいることが多く、利活用についてどこに相談すれば良いのか分からないのです。また、利活用について兄弟間で争いになってしまうケースも多々あります。兄弟の一人が売却することを主張し、別の兄弟が売却に強く反対するといった具合です。両方とも親の気持ちを代弁しますが、どちらの主張が正しいとも言えず、妥協することも難しいのが現状です。
空き家である間は適正管理が必要
自宅や実家が空き家になってしまう理由は十人十色。さらに、利活用ができるようになるまで数年、長いと10年以上かかることもあります。その間、誰も利用していない住宅は一気に傷んでしまいます。老朽化が進むと屋根や外壁などの建材が剥がれ落ちたり、建物が傾いて倒壊する危険性が高まったりとさまざまな問題を引き起こしてしまいます。
また、庭の管理が不十分な場合、生い茂った庭木や雑草が景観を乱すだけでなく、蚊やスズメバチや害獣(ネズミやハクビシン等)を発生させてしまうこともあります。そうならないためにも、所有者は所有する空き家を適正に管理する必要があります(所有者が管理できない場合はその配偶者や子供が代理で適正管理を行う必要があります)。
空き家の管理が行き届いておらず、周辺環境に悪影響を及ぼしてしまっている場合、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、行政からの指導や処分が行われるようになりました。自身での管理が難しい場合は空き家専門の代行業者に依頼しましょう。